その本の「はじめに」には、著者の「伝えたいこと」がギュッと詰め込まれています。この連載では毎日、おすすめ本の「はじめに」と「目次」をご紹介します。今日はシェーン・パリッシュ(著)、土方奈美(訳)の『 CLEAR THINKING(クリア・シンキング) 大事なところで間違えない「決める」ための戦略的思考法 』です。
【はじめに】Preface
2001年8月、私は情報機関で働きはじめた。ほんの数週間後の9月11日、世界が一変した。
たちまち組織で働く者は一人残らず、身の丈を超える役割や責任を背負わざるを得なくなった。私もしばらく前まで誰もできるとは思わなかったような任務を、次々と実行する方法を考えることになった。先例のない、複雑な問題を解決しなければならないだけではない。そこには人の命が懸かっていた。失敗は許されなかった。
ある晩、午前3時に私は自宅に向かって歩いていた。一つの軍事作戦が終わったところだったが、結果は期待したようなものではなかった。翌朝には上司のところへ行って、何が起きたのか、自分がなぜあのような選択をしたのか説明しなければならない。
私はすべてをクリア(明晰)に思考しただろうか。何か見落としがあったのか。どうすればそれを確かめられるのか。
私の判断が俎上(そじょう)に載せられ、審判を受ける。
翌日、上司のオフィスに行き、自分が何をどのように検討したのか説明した。話し終えてから、自分にはこれだけの仕事、これほどの重責を担うだけの備えがまだできていないと訴えた。上司は手にしていたペンを置き、深く息を吸ってこう言った。「備えができている者などいないよ、シェーン。でも君と、このチームでやるしかないんだ」
あまり慰めにはならない返答だった。ここでいう「チーム」に所属する12人のメンバーは、もう何年も週80時間働きつづけていた。そして「やるしかない」のは、この情報機関でも数十年ぶりという重要なプログラムを新たに立ち上げることだ。短いミーティングを終えて部屋を出たときには、頭がくらくらしていた。
その晩、私は10年にわたって考え続けることになる問いと初めて向き合った。
どうすれば論理的な思考力を高められるのか。
なぜ人は誤った判断を下すのか。
同じ情報を与えられて、他の人より常に優れた結果を出せる人がいるのはなぜか。
人命にかかわる状況で、どうすれば正しい判断の確率を高め、不本意な結果になる確率を抑えられるのか。
それまでの職業人生において、私はかなり運に恵まれてきた。それが続くに越したことはないが、運に頼る部分を減らしたい。クリア・シンキング(明晰な思考)や優れた判断をするためのメソッドがあるのなら、なんとかモノにしたいと思った。
モノの考え方、意思決定の方法をきちんと教わったことがある人は少ないのではないか。学校には「クリア・シンキング入門」のような授業はない。世の中には、そんなものは知っていて当然、あるいは独学で身につけて当然という空気がある。だが実際にモノを考える方法、それもクリアに思考する方法を習得するのは驚くほど難しい。
それから数年というもの、私はより良い思考法を学ぶことに没頭した。ほかの人々がどのように情報を入手し、分析し、行動に移すか、その行動が好ましい結果をもたらすか否かを観察した。単に他の人より頭の良い人がいるということなのか、それとも優れた仕組み、あるいはノウハウがあるのか。本当に重要な場面で、思考の質など意識している人はいるのだろうか。どうすれば明らかなミスを避けることができるのか。
幹部陣の会議にもついていった。黙って*話に耳を傾け、彼らが何を、なぜ重要だと判断するのか理解しようとした。認知に関する文献を片っ端から読み漁り、電話で話を聞かせてくれる人には質問を浴びせた。
周囲が混乱しているときでも、常にクリアな思考ができるインテリジェンス界の達人たち†とも連絡をとった。彼らはふつうの人が知らない何かを知っているようで、何としてもそれを突き止めたかった。
凡人は「勝ち」を追い求めるが、一流の人々は「勝ち」よりもまず「負け」を回避しなければならないことをわかっていた。実はこれが意外なほど有効な戦略なのだ。
学んだことを記録するため、私は「ファーナム・ストリート」(fs.blog)というウェブサイトを匿名で立ち上げた‡。判断することを生業(なりわい)とし、私の世界の見方に多大な影響を与えたチャーリー・マンガーとウォーレン・バフェットに敬意を表したネーミングだ§。
この間、私にとってのヒーローであるチャーリー・マンガーやダニエル・カーネマンから思考や意思決定について話を聞けたこと、さらにはビル・アックマン、アニー・デューク、アダム・ロビンソン、ランドール・スタットマン、カット・コールら達人たちと話ができたのは幸運だった。こうした対話の多くはポッドキャスト「ザ・ナレッジ・プロジェクト」で公開している。一方、マンガーと過ごした時間など、公開できないものもある。ただ、これほど錚々(そうそう) たる顔ぶれと対話を重ねてきたものの、友人のピーター・D・カウフマンほど私の思考やアイデアに影響を与えた人物はいない。
* 正確に言えば、「ほぼ黙って」
† 情報機関で働いていると、開かないと思っていた扉が開くことも多い。
‡ 匿名にしたのは、CIAやFBIといったアルファベット三文字の組織は、職員がプロフィールを公開するのに難色を示す傾向があったからだ。最近は状況も変わった。人材採用がきわめて難しくなったためで、今では職員がプロフィールを公開することも認められるようになった。担当業務を曖昧にしつつ、リンクトインのプロフィールに所属する情報機関の名前を明記している職員も多い。ただ私がサイトを始めた当時、情報機関は存在しないことになっていた。建物に看板もなかった。身元を明かせるようになるのは、それから10年以上先のことだった。
§ バフェットがCEOを、マンガーが副会長を務める投資会社バークシャー・ハサウェイの本社はネブラスカ州オマハのファーナム・ストリートにある。
何千という対話から一つ、決定的な気づきが得られた。
望みどおりの結果を得るために、私たちがやるべきことは二つある。まずモノを考え、感じ、行動するときに論理的思考の入り込むスペース(余地)をつくらなければならない。次にそのスペースをクリアな思考のために意識して使わなければならない。このスキルを習得すれば、圧倒的強みになる。
クリア・シンキングによって意思決定をしていると、徐々にあなたの立場は強くなっていく。成功はその積み重ねからしか生まれない。
本書はクリア・シンキングをマスターするための実践的ガイドだ。
前半のテーマはクリア・シンキングのためのスペースをつくる方法だ。最初にクリア・シンキングを阻む敵を挙げていく。私たちが「思考」だと思っているものの多くが、実は合理性とは無縁の、人間という種を保存するために進化した生物的本能から生まれる「反応」に過ぎないことがわかるだろう。合理的思考抜きにただ反応すると、自分の立場が弱くなり、選択肢は次第に乏しくなっていく。生物的トリガーへの反応をパターン化してしまえば、クリアに思考するスペースが生まれ、立場は強くなっていく。続いて、プレッシャーのかかる場面でも常にスペースを生み出せるように、弱みをコントロールし、強みを強化するためのさまざまな実用的かつ実践可能な方法を見ていく。
後半のテーマはクリア・シンキングを実践する方法だ。強みを強化し、弱みを制御できるようになったら、その結果何かを考えてから行動するまでの間にひと呼吸おけるようになったら、クリア・シンキングを優れた決定につなげられるようになる。第4部では問題解決に非常に有効な実践的ツールを紹介する。
デフォルト(素=す)の状態が自分にとってマイナスではなくプラスに働くようにコントロールし、合理的思考能力というツールを最大限に生かせるようになったら、最後に最も重要な問いと向き合う。「そもそもあなたは何を目指すのか」だ。どれほど遂行力が優れていても、それが正しい結果をもたらさなければ何の意味もない。では目指す価値のある目標をどう見きわめるのか。
本書では効果的な思考法を、類書とは違ったかたちで紹介する。しゃれた専門用語やエクセルシート、フローチャートなどは使わない。私が他の人から学び、あるいは自力で発見し、そのうえでさまざまな組織、文化、業界で何千人という人々に試してもらった実用的スキルに絞って見ていく。
行動科学と私たちをとりまく現実の分断を埋め、ともにありふれた瞬間から圧倒的成果を生み出していこう。
本書の教えはシンプルで、実用的で、普遍的だ。土台となっているのは私が他の人々から学んだ知恵と、それらを自ら実践するなかで得た経験である。こうした教訓や知恵を、私は情報機関でより優れた決定を下すうえで、その後は複数の事業を立ち上げて成長させるうえで、さらには意外かもしれないがより良い親になるために生かしてきた。どのように生かすかはみなさん次第だ。
私の人生にキャッチフレーズがあるとすれば「他の誰かがすでに導き出した最高の成果をマスターする」であり、本書はその信念を地で行くものだ。個々の知見の出所はできるかぎり明記するようにしたものの、おそらく抜けもあるだろう。それについてはお詫びしたい。学んだことを実践すると、それは自分の一部となる。
20年にわたって世界一流の方々と何千という対話を重ね、数えきれないほどの本をむさぼるように読んできた今となっては、一つひとつの知識をどこで得たかを思い出すのは容易ではない。大部分はすでに私の無意識に組み込まれている。本書に何か有益な情報があるとすれば私以外の誰かが生み出したものであり、私の主な貢献は先達から学んだことをモザイクのようにまとめて世に送り出したことと言って間違いないだろう。
【目次】
からの記事と詳細 ( はじめに:『CLEAR THINKING(クリア・シンキング) 大事なところで間違えない「決める」ための戦略的思考法』 - 日本経済新聞 )
https://ift.tt/PAqhaiF
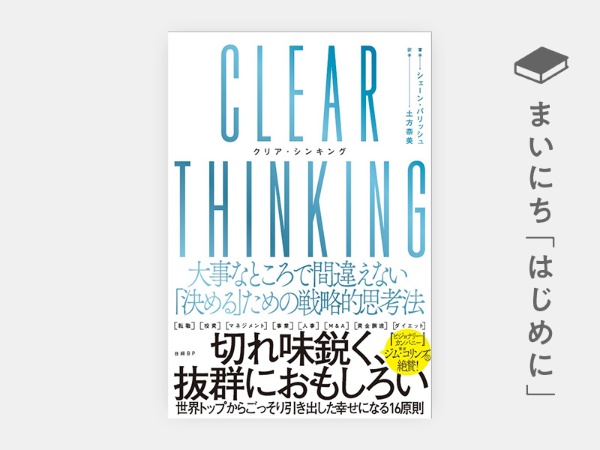

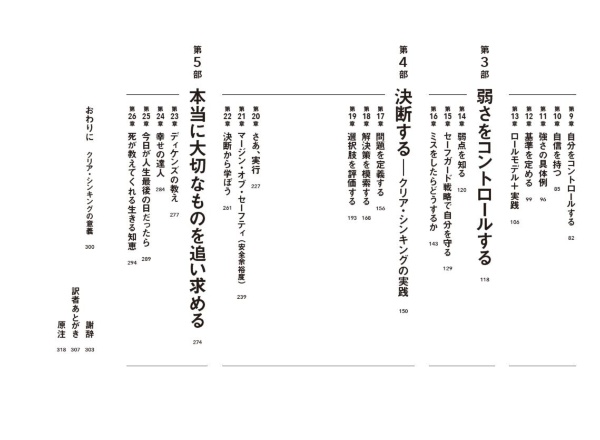
No comments:
Post a Comment