▼距離を保ち 黙って給食
新型コロナウイルスの第六波は園児や職員らへの感染が深刻化し、保育施設が休園を余儀なくされる事態が相次ぐ。「三密が避けられず、安全な保育が分からない」。保育士からは、そんな不安も漏れる。感染対策に細心の注意を払う石川県小松市の保育所を記者が訪ねた。(久我玲、写真も)市街地から少し離れた舟見ケ丘保幼園(河田町)。ゼロ歳から六歳まで二百二人の子どもを受け入れ、保育士や看護師、調理師ら計五十五人の職員が働く。
午前八時ごろ、送迎バスや保護者の車で園児たちが登園してきた。玄関には園児の背丈に合わせた消毒液。保育士は、小さな手のひらにシュッと一吹きした後、一人一人の顔色を確認し、体調を気に掛ける。
正午すぎ、五歳児クラスではアクリル板で仕切られたテーブルが並んだ。給食時間だ。「食べるときはおしゃべり我慢ね」。担任保育士は呼び掛ける。園児たちは思ったよりも静かに食べている。そのテーブルから二メートル離れた距離で、保育士は黙って食事。「本当はお箸の持ち方を教えたり、おいしいねって会話しながら食べたいんですけどね」
絵本の読み聞かせも、お遊戯会の練習も、園児同士の距離は保たれている。こうした環境の中、最も労力を使うのが園内の消毒作業だ。お昼寝の時間を使い、園児の手が届く高さの壁や窓、手すりなど、複数の保育士で消毒。すやすや眠る園児たちの隣で、保育士たちは忙しく動き回る。おもちゃを一個ずつ丁寧に拭く姿もあった。
▼「成長に大事な時期が」
おんぶや抱っこなどの接触が欠かせないゼロ歳児の三十代保育士が、胸中を明かす。「担当の園児がPCR検査を受けると知るとドキリとする。自分の休日の行動を振り返り、園児にうつしてしまっていることがないか、緊張する」。こうした声を聞き、園児や保育士の差別への配慮の必要性も痛感した。中尾峰子園長は「子どもの成長に大事な時期。いろいろな経験の機会が奪われている。いつ休園になってしまうかも、分からない。暗中模索の日々です」。
◇ ◇ ◇
県内の認可保育施設は三百六十五施設。県の健康福祉部少子化対策監室によると一月下旬から休園数が増え始め、今月十二日には全体の約7%に当たる過去最多の二十五園が休園になった。
「金大病院小児科・和田主任教授に聞く」
園児の感染防止の難しさ、不安は尽きない。保育現場でどう対処するべきか、日本小児感染症学会の新型コロナに関するワーキンググループ代表で金沢大病院小児科の和田泰三(たいぞう)主任教授に聞いた。
A 子どもでも二歳未満や基礎疾患があれば重症化リスクがあります。保護者が仕事を休まざるを得ず、休園すれば学びの機会や栄養バランスの良い給食を食べる機会も失われます。
Q 休園の判断基準は。
A 難しい問題です。最新の知見を基に関係各所で協議し、決めていくことが望まれます。感染者との接触状況を確認し、休園は必要以上の広範囲とせず、期間の無用な延長も避けることが求められます。濃厚接触者でなければ健康観察を続けながら登園を妨げないことも大切です。
Q 二歳以上はマスクが推奨されている。
A 二歳以上の子どもでも、発達の問題など事情を抱えている場合があり、一律に着用を求めることは慎重であるべきです。適切に着用できなければ、手でマスクを触ることで接触感染のリスクが高まることも予想されます。
Q 子どもたちとのふれあいで気を付けることは。
A 職員がマスクをしていると、表情による意思疎通がとりにくい現状もあると思います。表情を少し大げさにしてわかりやすくしたり、声掛けやしぐさでふれあいを多くとったり、工夫してほしいと思います。
関連キーワード
おすすめ情報
からの記事と詳細 ( 【石川】安全な保育 手探り 「休園不安」 小松の保育所ルポ - 中日新聞 )
https://ift.tt/xW8UpbB

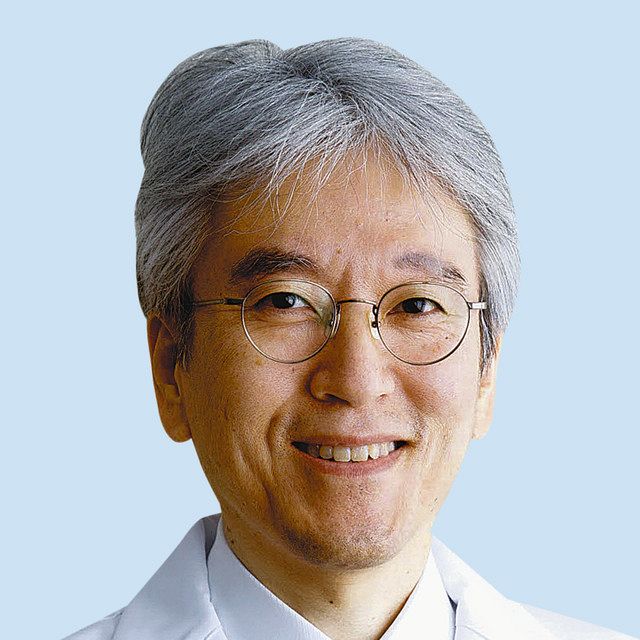
No comments:
Post a Comment